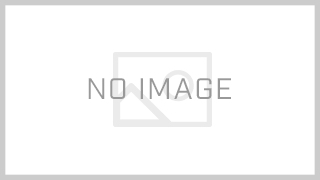今回のブログは
「JRの学割を使って、601キロ以上(か、それよりちょっと短い距離。東京~大阪間など)を往復する人に向けてのもの」
に特化しています。
他に知りたいことがある人は、↓のブログへどうぞ。
基本的な学割の計算法を知りたい
>>>JR学割きっぷの値段の計算方法 電卓で計算できる!
学割証が何枚あればいいのか知りたい(きっぷの有効期間など)
>>>結局、JRの学割証って何枚必要なの?この疑問に決着つけます
このブログでは、学校の人が分からない(と思う)レベルのことを解説しています!
この先、読んでいてよくわからないな・・・と思ったら
学割の基本的なことが書いてあるこのブログを先に読んでみよう!
>>>JR学割きっぷの値段の計算方法 電卓で計算できる!
JR往復割引の基本
 JRでは
JRでは
片道601キロ以上の区間を往復する場合
乗車券の運賃(=きっぷ代)が1割引になります(10%オフ)
これを「往復割引」といいます。
いっぽう、学割は
乗車券の運賃(=きっぷ代)が2割引になります。
(特急券は割引にならない)
そして、ここが重要。
この往復割引は
学割と同時にダブルで使うことができるのです!
<割引の計算方法>
1割引きは
元の値段に0.9を掛け算したらOK
2割引きは
元の値段に0.8を掛け算したらOK
学割と同時にダブルで使う時は
0.9と0.8の掛け算を2回します。
10000円のきっぷ代の場合
10000×0.9×0.8
=7200円
スマホ電卓で計算してみよう!
往復割&学割の計算方法
細かい
往復割引と学割をダブルで使う場合の割引の計算方法はこの通り。
「片道の値段に0.9を先にかけてからそれを端数(はすう)処理し、その値段にさらに0.8をかけて端数処理をする」
端数処理とは
「掛け算をして出てきた1の位の数を0にする」
という意味。
13750×0.9を掛け算すると
12375になります。
1の位は「5」ですね。
四捨五入だと
繰り上がって12380になりますが
今回は「1の位の数を0にする」なので
5以上の数字も、全部0にします。
12375を端数処理すると
12370になるのです。
じゃあ
具体的な計算をしてみましょう。
例:神戸市内から盛岡(岩手県)までの運賃
片道の定価は 13750円
13750×0.9=12375
端数処理で 12370
12370×0.8=9896
端数処理で 9890
片道の学割&往復割は
9890円
往復の運賃は
9890円×2=19780円
ぶっちゃけると
先に0.9をかけても、先に0.8をかけても、ほとんどの場合同じ計算結果になります。
なので、本当は順番はどっちでもいいんですが
(端数処理を2回するのは忘れずに!)
たまーに
計算結果が10円くらいズレることがあります。
先ほどの神戸市内→盛岡の運賃を
先に0.8をかけて計算すると、片道の運賃が9900円になり
実際の往復運賃より20円高くなってしまいます。
600キロ以下の移動も安くなる?!
学割の話はだいたいこれで終わりですが、最後はおまけレベルのお話。
往復割引が使えればいいけど、どうしよう・・・?」
そんな場合のお話です。
東京~大阪(556.4キロ)間や
東京~神戸(589.5キロ)間などを移動するときに、とっても!役に立ちます。
JRのきっぷは
「きっぷに書かれた出発駅から乗って、書かれた目的地の駅に降りないと絶対にいけない」
そう思っていませんか?
実は、そんなルールはないのです!
(一部の特殊なきっぷは除く)
2つの駅の間のルートの途中の駅から乗ってもいいし
最終目的地の手前の駅で降りて、そのままきっぷを捨てて旅行を終えてもなにも問題はありません。
例:東京から新神戸までの乗車券を持って移動する場合(東海道新幹線経由)
ルートの途中にある新横浜駅から乗って、最終目的地(新神戸)の手前である新大阪で降りても良い。
(距離が短くなったからといって、返金はされない。ただし最終目的地までの距離が101キロ以上残っている場合は手数料を差し引いて払い戻し可能)
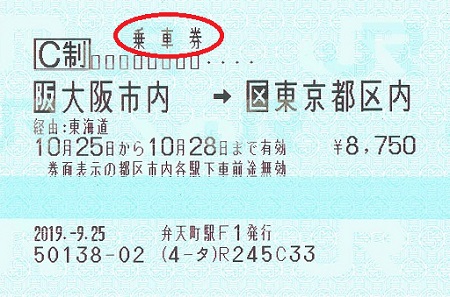 ※必ずしも、大阪から乗って東京で下りないといけないわけではない。「経由」と書かれた路線上(このきっぷのルート上)なら乗り降りする駅は自由(引き返すのはダメ)
※必ずしも、大阪から乗って東京で下りないといけないわけではない。「経由」と書かれた路線上(このきっぷのルート上)なら乗り降りする駅は自由(引き返すのはダメ)
そうなれば、話はカンタン。
「距離を伸ばして、片道601キロ以上のきっぷにする」
これで解決。
特に大きな効果を発揮する区間のひとつが「東京~神戸」間です。
東京~神戸の片道乗車券の定価は9460円。
(学割適用後は7560円)
距離は589.5キロなので、ギリギリ600キロに届かない。
惜しい!もったいない!
そこで
行き先をお隣の明石市にある、西明石駅まで伸ばしましょう。
東京~西明石間の片道乗車券の定価は9610円。
距離は601キロ以上なので、往復割引が適用されます。
往復割引で、値段は8810円に。
さらにこれに学割を重ねると
7040円に。
なんと!
東京~神戸の学割7430円と比較して、片道あたり520円も安くなりました!
往復で1040円!
これは無視できない金額ですね。
きっぷの使い方はいたってシンプル。
新幹線で新神戸駅まで向かい
そこで自動改札にきっぷを通すだけ。
(新神戸は、東京~西明石のルートの途中にある駅なので、下りても大丈夫)
万一自動改札でエラーが出たら
慌てず駅員さんに「途中下車です」と言って降りましょう。
これでおしまい。
逆に神戸から東京に向かう場合は
普通に新神戸の駅で改札を通して、あとは東京へ向かうだけ。
おしまい。
以上のようなテクニックは
「東京~大阪間」でも使えます。
東京~大阪の乗車券は片道8910円。
(学割適用後は7120円)
これを、神戸の場合と同じく「東京~西明石」の乗車券にして
往復割引と学割を適用させると、片道の値段は7040円。
つまり、片道あたり80円
往復で160円の得になるわけです。
・・・まあ、この場合はそんなに得にはならないけど
こういう方法もあるのね、と知ってもらえたら幸いでございます。
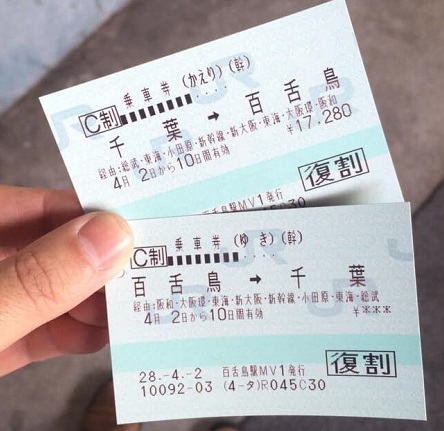 ※百舌鳥(もず。大阪にある駅)~千葉(千葉県)の往復乗車券。
※百舌鳥(もず。大阪にある駅)~千葉(千葉県)の往復乗車券。
一見、千葉へ行くきっぷだが、実はこのときの旅の最終目的地は東京。
百舌鳥~東京の往復乗車券の値段は17920円(600キロに満たないので割引無し)。
これを無理やり千葉駅まで伸ばしたので、600キロを超えて、往復割引で合計17280円になりました。往復で640円の得。(値段は消費税8%時代のものです)
ここまで読んでくれたあなたへ
マニアックなテーマでしたが
よくここまで読んでくれました。ありがとうございます。
ここからはボーナスステージということで
もっときっぷ代がお得になるテクニックを、2つご紹介しましょう。
1つは「途中下車」
例えば、東京~大阪を旅行会社のツアーなどで新幹線移動すると
途中の都市に立ち寄って観光することはできません
(名古屋・静岡など)
でも、学割の新幹線きっぷだと
場合によっては、ちょっとのお金の追加(追加しなくてもいける場合あり)で
途中にある都市に立ち寄ることができるのです!
例えば、大阪~東京間の移動なら
1000円くらいの追加で、途中の沼津(ぬまづ)に立ち寄って
ラブ○イブ聖地巡礼などをすることもできます。
京都や横浜なら
追加料金不要(場合によっては安くなることもあり)で巡ることも可能です!
詳しくはこのブログを読んでみよう!
>>>鉄道旅行最大の魅力!途中下車とはどんなルールなのか?
2つめは
「東京フリーパス代わりに使う」
東京を観光する時限定ですが
1日700円とか1000円するようなフリーパスを買わなくても
実質、学割の新幹線きっぷを、東京の中心地のフリーパスのように使うことができるテクニックです。
詳しくはこのブログを読んでみよう!
>>>JR70条区間途中下車や新幹線ルール 普通切符が東京フリーパスに?